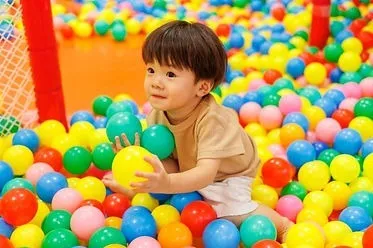お子さんのペースを大切にしたサポート
ことばの発達に関する悩みは、ご家族にとって大きな関心事です。お子さんのペースを大切にしながら、適切なサポートを受けることで、日々の会話やコミュニケーションがより豊かになります。言語聴覚士としての知識と経験を活かしながら、一人ひとりに寄り添って支援しています。また、成長をあたたかく見守りながら、家庭や園での関わりがより楽しくなるようお手伝いをしています。
fluffyについて
ごあいさつ・自己紹介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
ことばの発達サポートfluffy(フラフィ)代表の多部未来(たべみく)と申します。
2009年に言語聴覚士資格を取得し、発達医療センター、保育園、児童発達支援事業所で勤務し、1,530人以上のお子さんとそのご家族に寄り添ってまいりました。
また、”保育所等訪問支援”で6年間、約15の園、35名以上のお子さんと向き合い、
先生方や保護者さんに、実践的なサポートを提案し、お子さんの発達をサポートしてまいりました。
「何かしてあげたいけれど、どう関われば良いのだろう…」
「平日は忙しいけれど、休日に少しでも子どものためにできることをしたい!」
そんなご家族の想いに応えるサポートを、ことばの発達サポートfluffyは提供しています。
お子さんやご家族のお気持ちや生活スタイルに寄り添い、ご家族が日常生活の中で無理なく取り組める関わり方を一緒に考え、提案していきます。
また、クラスで支援が必要なお子さんとの関わり方に悩んでいる先生方にも、ことばの発達サポートfluffyは一人ひとりのお子さんが過ごしやすいクラス運営ができるよう、具体的で実践しやすいアドバイスをご提案します。
タンポポの綿毛のようにふわふわと、ご自宅や園に訪問し、ことばの発達サポートfluffyはお子さんの成長をしっかりと見守ります。
大切なお子さんが、ご家庭や園で根を張り、自分らしく咲き誇れるお手伝いをいたします。
まずは、お気軽にご相談ください♪
言語聴覚士 多部未来
私がなぜ小児の言語聴覚士になったのか、
なぜことばの発達サポートfluffyを立ち上げたのかを少しお話しさせていただきます。
小児の言語聴覚士になろうと思ったキッカケ
私には“知的しょうがい&自閉傾向”のいとこがいます。
その子が言語聴覚士の個別訓練を受けていました。
20数年前、言語聴覚士は10,000人にも満たない程でした。
(2024年3月に40,000人超えました。ただ、小児の言語聴覚士は5,000人程です。)
その子のお母さん(叔母)に
「小児の言語聴覚士って少ないから、そのうち言語訓練が受けられなくなるの…。だから、言語聴覚士になって!」
と言われました。
インターネットで言語聴覚士や言語聴覚士の養成校を調べたら、こどもと楽しそうに関わっている画像があり、「楽しそう♪」と思いましたし、“国家資格”という点にも魅力を感じました!
高校生の時に「言語聴覚士になろう!」と決意し、専門学校に入学するための勉強をして、無事入試に合格しました!
専門学校では、基礎的な学問や専門的な学問を学び、実習で様々な経験を積ませてもらいました。
夏休みには、小児施設や成人の病院に見学に行きました。
小児施設では身体を動かすことが多く、体力は消耗しているはずなのに、元気をもらって見学を終えていました♪
お子さんの笑顔からパワーをもらっていることを実感し、改めて「小児の言語聴覚士になろう!」と決意しました!
発達医療センターでの経験と気付き
発達医療センターでは、1〜6歳のお子さんを対象に保護者さん同席のもと、言語訓練や食事訓練を行ってきました。
その中で、知能検査、発達検査、言語検査、聴力検査などの必要な検査をとり、お子さんの様子と保護者さんからの聞き取りと照らし合わせて、訓練プログラムを考えてアプローチしてまいりました。
対象のお子さんの診断名は様々で、自閉スペクトラム症、知的障害、脳性麻痺、染色体異常など、たくさんのお子さんと関わってきました。
ただ、刺激の少ない訓練室でできることでも、園ではなかなかできないことがあることを、保護者さんからのお話を聞いて知りました。
こちらが「こういう支援が園でできると良いですね!」と保護者さんにお伝えしたことも、現実的な提案ではないのではないかと感じるようになりました。
そこで、実際にお子さんが長時間過ごす保育園で働いてみようと思い、保育園に転職しました。
保育園での経験と気付き
保育園では保育補助として勤務しました。
1箇所目は系列の保育所の人手が足りない所に日々派遣という形で働きました。
系列の保育所でもハード面が異なったり、様々なタイプの先生がいらっしゃることを肌で感じることができました。
また、乳児クラスに入ることが多く、乳児さんと接する機会が多々ありました。
元々、発達医療センターでことばが出ないお子さんとたくさん関わってきた経験がありますので、自然とお子さんの気持ちを代弁したり、発達を促すようなことば掛けをしたりしていました。
一緒に働かせていただいた保育士さんには「安心してお子さんとの関わりを見ていたよ」と嬉しいことばをいただきました。
2箇所目は1つの保育園に約1年間勤務しました。
1年間一緒に過ごすことで、各年齢のお子さんの成長を感じることができました。
専門学校の時にお子さんの発達は勉強していましたが、保育園のお子さんと関わるなかで、同年齢でも様々なお子さんがいることを改めて認識することができました!
主に年少さんのクラスに入らせていただきましたが、集団活動への参加が難しいお子さんの対応もしてきました。
お子さんの上手く伝えられない気持ちに寄り添って、一緒にゆったり過ごし、
「最後はやる?頑張っているところを見ているからね♪」
と集団活動に送り出すサポートをしました。
また、保育士さんが実際に保育をされているのを間近で見て、大人数のお子さんをまとめる上手なことば掛けや、先生同士の連携、日々の保育や行事の準備など、保育園の中で働かせていただいたお陰で、先生方の日々の大変さも知ることができました。
児童発達支援事業所での経験と気付き
児童発達支援事業所では、個別指導、ミニ集団療育、保育所等訪問支援の業務に携わっていました。
個別指導では、保護者さん同席のもと、1対1での言語訓練や食事指導を行いました。
お子さんの現状を保護者さんと確認し、お子さんの発達が伸びる関わりを実践し、ご家庭でも取り組んでいただくようお伝えしました。
ミニ集団療育では、保育士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士と、他職種の職員と一緒にお子さんの療育を行いました。
他の職種の職員とお子さんのことを多面的にみて、アプローチしてまいりました。
今までは言語聴覚士の視点でしかお子さんを見ていなかったので、新たな視点を持つことができました。
保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所を利用されているお子さんの幼稚園や保育園に伺って、園でのお子さんの様子を拝見し、園の先生と情報共有を行い、お子さんが園で過ごしやすい関わりを一緒に検討させていただきました。
その中で、現場の先生方が他のお子さんの対応方法に悩まれている状況を目の当たりにし、「クラス全体を見て、お子さんや先生方へのサポートが必要だ」と感じる場面が数多くありました。
改めて、保護者さん同席のもとでお子さんを指導し、ご自宅で取り組めそうなことをご提案することや、困っている現場でのお子さんの様子を見て、現状の困り感をどう解決していくのかを現場の方と話し合う大切さを感じました。
保護者さんからご家庭でのお悩みを相談されることがありましたが、実際にご自宅に伺って実現可能な解決策を一緒に考えていけたら良いなと感じました!
また、療育を受けたくても、保護者さんのお仕事の都合で通わせることが難しいご家庭があることも感じていました。
これらの経験から、ご家庭のニーズに応じて訪問し、保護者さんと一緒にお子さんの発達を支える
<ことばの訪問サポート>と、
園全体を対象にした支援でクラス運営をスムーズにする
「クラスまるごとサポート>の両方が必要だと考えました。
また、遠方にお住まいの保護者さんから「多部さんに相談したい!」とのご要望がありましたので、
<オンラインサポート>も開始しました。
それぞれのサービスを通じて、お子さんの成長を多方面から支える体制を整えたいという想いで
《ことばの発達サポートfluffy》を立ち上げました!
これからも、お子さん一人ひとりに寄り添い、ご家庭や園での成長を一緒に見守りながら、日常生活に役立つ具体的なサポートをお届けしていきます。